|
<原文>
知雨亭[1]とは、隠栖[2]の穴居[3]に類すべく、巣居[4]の風を知り、穴居[3]は雨を知るの心を以て云り。又半掃庵[5]とは、我物ぐさ[6]の明くれ、掃く日よりは掃ぬ日は多く、床は塵、庭は落葉に任せがちなる庵のだゞくさ[7]をいふなりけり。名はふたつにして物二つならず。されば是に七景を撰ぶ。
東嶺孤月[8] 路傍古松[9] 蓬丘烟樹[10]
海天新雁[11] 龍興寺鐘[12] 市門暁鶏[13]
隣舎舂歌[14]
東嶺孤月[8]とは、嶺は三河の猿投山なり。遠き山々の夫より北につらなりて、此山のあはひより、十月ばかりのよく晴れたるには、士峰[15]のいたゞきもみゆる事あり。夫かあらぬか[16]と、昔は人の疑ひしが、宝永の比、かの山の焼ける時、夫とは定まりしかと、古き人のいへりけり。さればさなげ山とは、名のをかしくて歌などにも読むべきを、文字を猿投と書けるは少しくちをし。たゞ万葉にぞかゝまほしけれ。されど月には猿の名もよそならず。ほとゝぎすも蜀魂[17]と書き、朝がほも牽牛[18]とかけばむくつけき[19]たぐひにや。清氏の女[20]も絵に書いて劣るものと言っているが、字に書いて劣るということはない。月は夜の長短によって、この山の南北より出でて、清光[21]ことにさはる物なし。此府下に月の名所をえらまば、此地をこそいふべかりけれ。
路傍古松[9]とは、世に七本松とよべり。あるは相生[22]めきてたてるもあり、又程へだゝりてみゆるもあり。染めぬ時雨のゆふべ、積る雪の朝、ながめことに勝れたり。草薙の御剣[23]のむかし語を追ひて、もしは此七つを以て辛崎の一つにかへむといふ人ありとも、我は更におもひかへじ。
蓬丘烟樹[10]は、則ち熱田の御社なり。高蔵の杜は猶ちかくて、春の霞、秋の嵐、此亭の南の観、たゞ此景にとゞまる。しばらく杖を曳けば[24]、あけの華表[25]も木の間にみゆめり。鳴海は熱田につらなりて、松風の里・夜寒の里・呼継浜・星崎など、我国の歌枕は、皆此あたりにあつめたり。すべて是熱田の浦辺なれば、海づらもやゝみゆべきほどなれども、家居にさわり森にへだちて、一望のうちにいらず。
されば、海天新雁[11]も、此あたりをいへるなりけり。
龍興寺鐘[12]は、庵の東よき程に隔たる木立一村の禅林なり。ある日客ありて物語しける折しも、此鐘のつくづくと雲よりつたふを聞きて曰く、「けふ此声の殊に身にしめる何ぞ然るや」と。我是に答へて曰く、「客もかの廿年[26]の昔をしるならん、此あたりはしばし歌舞の遊里[27]となりて、あけ暮糸竹[28]のえむをあらそひ、月雪花[29]もたゞ少年酔客の遊にうばゝれしが、其世は此鐘の暁ごとに別を告げて、幾衣々の腸をたちけむ[30]。世かはり事あらたまりて、今は其形だになく、蛾眉[31]蝉鬢[32]も今いづくんかあるや。されば、つく人に心なくとも、聞く人の耳にのこりて、遺響[33]を悲風[34]に託せるならん」と。客も実にと聞きて、かついたみ、かつ笑ひにき。
さてや、市門の暁鶏[13]は、此西の方、あやしの小借屋といふ物、軒をならべ、おのがさまざまの世渡り佗しげなれど、かゝればおのづから遠里小野[35]のかはりかりの声も、事かゝぬ程に音づれ、はかばか敷商人は来らね共、海老・鰯・小貝やうの物、名のりて過ぐる事も明くれなり。さればたまたまとふ人ありて、みさかな[36]に何よけんなど、一盃をすゝむるには、こゆるぎのいそぎありかねども、居ながら求め得る日も有るべし。家ゐは是より市門[37]へつらなれば、暁の鳥も枕につたへて、老のね覚のちからとはなれる也。
隣舎舂歌[14]は、もとより農家の間なればいふにも及ばず。かのからうす[38]のこほこほ[39]となりし夕がほの隣どのは、なほゆたかなる家ゐにてもやありけん。こゝらは唯手杵[40]の業わびしく、麦の秋・稲の秋、あはれは砧[41]の丁東[42]にもゆづらず。是をならべて七景とはなせりけり。さるはいとをこがましく、遼東[43]の豕にも似たれど、賞心[44]は必ずしも山水の奇絶[45]にもよらじ。名にしあふみの人のみるとも、おのが八所の厚味[46]にあかば、かゝる淡薄[47]のけしきも又まづらしきにめでゝ、一たびの目をとゞめざらめや。
昭和58年3月30日 名古屋市教育委員会発行『名古屋叢書三篇 第十七巻・第十八巻 横井也有全集 中』より
|
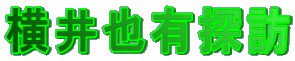

![]()