|
<原文>
こはそもはかなき[1]世なりけり。過ぎしはわづかに二十日あまり、武蔵[2]に旅立する御いとま[3]申さむとて訪ひ参らせしに、例のまめやかに[4]もてなさせ給ひ、のどやかに[5]御物語[6]ありしが、御前[7]なる瓶に花ども多く挿させ置き給ひしにつけて、「過ぎし冬、桜の挿し木といふこと人に習ひて庭にささせ侍りしに、まことにあやまたずなん」と啓し[8]侍りつれば、「嬉しきこと聞きつるものかな。今年の冬かならず挿させてむ。そのすべきやう教へて」とのたまはせし[9]ほどに、かかる[10]御別れあるべしとは思しかくべきや。なほ何くれと語りつづけさせ給ふついでに、「この頃、思し寄れることあり。下に賤し[11]の耕す男画きて、上つ方に雲雀[12]の高く上りたるさま画きて、それに発句[13]して得させよ」とありしに、「いとこちたく[14]こそ。すずろなる[15]筆のいかが、及びがたくや侍らん。今は旅の急ぎに静心[16]なく侍れば、さるべき発句[13]もとみには思ひ寄りがたくなむ。さるにても吾妻[17]に下り侍りて、いかで[18]念じて、まほならず[19]とも画きととのへて奉りてむ」とうけがひ参らせし、その暇[20]もなくて、今はた悔しき数[21]とはなりぬ。
我が母上をはじめて、女の御はらから[22]九所までおはしつ。皆似げなからぬよすが[23]定まらせ給ひながら、うち続きて世を早う去り給ひ、今は二方ばかりぞ残りとどまり給へば、母上失せさせ給ひし後は、いとど御形見[24]とも見奉れば、なほざりに[25]過ぎ来しほども取り返さまほしう、「今は身のおほやけに[26]暇[20]なきものから、いかで疎からず[27]仕へ奉るをりもがな」と、行末[28]遠く思ひてしを、かかるはかなき[1]便り聞きける心の、いく度もただ夢かとぞたどられ侍る。かののたまはせし空の雲雀[12]も、雲隠れ給ふべきはかなき[1]さとしにやとさへ、残る方なく思ひ続くるままに、
なき魂やたづねて雲に鳴く雲雀[12]
昭和58年3月30日 名古屋市教育委員会発行『名古屋叢書三篇 第十七巻・第十八巻 横井也有全集 中』より
|
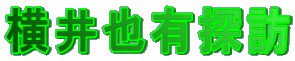
![]()