|
<原文>
此小ぶすま[1]の白くてさうざうしきに、物かきてえさせよとあるに、さらに何かくべしとも覚へず。されど辞してもゆるさるまじきかたを早くしりて、よしさらば此棚に鼠のあれぬまじなひせむと、おこがましく[2]筆とりて書たるは何ぞ。我は猫なりと思へども大宮人[3]はいかゞいふらん。昔、金岡[4]が書たる萩の戸の馬はよるよる萩を喰あらしたるとか。もしはさる能画[5]の筆して、四季のすゞみ清水の花見など、にぎはゝしき絵の屏風[6]襖にもあらば、あまたの人の夜毎に出て扶持方[7]もつゞきがたかるべし。我が袋戸[8]の猫は、たとへすゝけて[9]千とせふる[10]とも、赤手のごひ[11]の踊もしらず、まして肴のたなさがしもせねば、あるじの為は中々心安きかたならむを、朧月夜[12]にうかれぬのみぞ、玉の巵[13]の底なしとやそしられぬべき。 世につたなき筆の虎をゑがきては、必猫なりとわらわるれば、我又猫をうつさば虎にも似るべきを、杓子[14]にはちいさく耳かきには大きなりと、かの柿の木のむかし咄ならん。かくいへば鼠の為とてもよしなし事に似たれども、いでや鼠にも白黒の賢愚[15]ありて、子祭り[16]の白鼠はあるじもいさにくむまじければ、かしこく知りてさけぬもよし。心の鬼[17]のわる鼠のみ、これだにも気づかふべきは、落武者の薄の穂[18]を人なりとみるたぐひにて、少はそれよりも近かるべし。さらば牡丹花下にてふ[19]を驚かさむよりは、此棚にねぶりてかのわる鼠をいましむべしとかれにしめしの一句にいわく、
ゆだんすな鼠の名にも廿日草[20]
昭和58年3月30日 名古屋市教育委員会発行『名古屋叢書三篇 第十七巻・第十八巻 横井也有全集 中』より
|
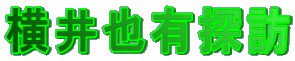
![]()